こんにちは。たかぼんです。
今回は、私が育休取得期間を決定するために検討したいくつかのポイントについてご紹介したいと思います。
育休取得期間は人によって前提条件や考え方が異なるため正解がないため、あくまで網羅的に検討すべきポイントをご紹介できればと思います。
私の状況は以下です。
夫である私が育休を取得している時点で、里帰り出産ではありません。
また、夫婦共働きのため、幼稚園ではなく保育園です。
- 子は一人目
- 子の出産は2024年9月末
- 通常の育児休業を取得(出産時育児休業制度ではなく)
※出産時育児休業制度を利用しなかった理由については別途ご紹介予定 - 育休取得期間は 2024年10月下旬から2025年4月中旬の約6ヶ月
- 妻は育休後、2025年4月に職場復帰予定
- 子どもは、夫婦の職場復帰に合わせ、0歳で保育園に入園予定
さて、結論ですが、以下のポイントで育休取得期間について検討しました。
- 出産予定日(開始)
- 保育園入園のタイミング(終了)
- 慣らし保育期間(終了)
- 育児休業給付金
- 社会保険料の免除(開始、終了)
- 有給消化(開始、終了)
- ボーナス査定期間(開始、終了)
私の中で重要なのは出産予定日と保育園入園のタイミングで、残りの4つは業務や勤務状況に応じて会社と調整できる内容だと思います。
こどもの育成方針もしかり、保育園入園のタイミング次第で、お互いの復職や今後のキャリア計画にも影響があるかと思いますので、奥様と協議・擦り合わせする時間を十分に設け、ご検討された方がベターだと思います。
詳細についても簡潔に以下に記載します。
出産予定日と育休開始について
出産予定日の1,2週間後から育休期間がベター、出産後は有給等で調整!
人により考え方は違うと思いますが、私は出産後の妻の退院に合わせ育休(有休消化含む)を開始しました。
お伝えしたい点は1つだけです。出産後、すなわち妻の入院中は、家にいても暇です。笑
たかぼん家では、出産の1ヶ月前くらいには様々な物品を揃え赤ちゃんを家に迎える準備ができていたため、正直家にいても持て余すからです。
なので、会社への申請の時点で、出産予定日の2週間後を育休開始とし、実際に育休期間になるまでの数日は、会社から支給される特別休暇と有給で調整できるようにしました。
この、有給で調整できるようにした部分が精神的にも良かったです。もし仕事がうまく引き継げなかった場合にも、育休ではなく有給なので、都合があえば出勤したり業務することができる、という安心感がありました。
保育園入園のタイミングについて
入園しやすい0歳児4月入園を選択!
たかぼん家は、0歳児4月入園を選択しました。理由は、
- 次の4月から復職予定だから(9月末出産)
- 夫婦とも復職予定のため、入園しやすい0歳児入園にしたかったから
です。
保育園入園は、0歳児と3歳児の4月が比較的入園しやすいと言われています。参考までに、以下簡潔な理由です。
0歳児が入園しやすい理由
- 1,2歳児クラスのように、進級により枠が埋まることがない
- 1,2歳児と比較してそもそも利用者数が少ない
利用者割合全体に対して、0歳児が5.0%、1,2歳児は35.4% 子ども家庭庁発表「保育所等関連状況取りまとめ(令和5年4月1日)」より引用
3歳児が入園しやすい理由
- 3歳から幼稚園を利用する場合があるため
以下、参考にさせて頂いたサイトです。
より詳細確認したい場合はこちらを参照いただくと良いかと思います。親から目線だけでなく子ども目線からも言及されていて、とても参考になりました。


慣らし保育期間について
慣らし保育期間がある可能性があることを念頭に!
個人的に意外と落とし穴なのが慣らし保育期間かと。
慣らし保育とは、いきなり通常保育ではなく、1日1時間などの短い時間から徐々に保育園の生活リズムに合わせていく期間の事を指します。
保育園の方針や自治体、保護者の就労状況によりが異なるかと思いますが、例えば4月入園であれば4月の数日〜数週間は慣らし保育期間になる場合があり、そうなった場合その期間は通常通り勤務ができない可能性があります。
もちろん、フレックスや半休、育休期間の変更を活用して対応することはできると思いますが、育休で長い期間業務を離れてた身で、復帰後にもいきなり職場に迷惑をかけるのは、、と考え、私は4月復職ですが、あらかじめ、育休は4月中旬まで取得することにしました。(4月中に復職すれば4月入園は可能)
また、妻の復帰タイミングは3月末で、4月からフルで職場復帰予定なので、保育園や登園に慣れない子どもや夫婦二人のことも考え、いきなり二人がフルで職場復帰にならないように配慮した結果でもあります。
育児休業給付金(育休手当)について
育休手当は180日以降、減る!
育休手当の給付金額は、以下のように定義されています。
支給額=
休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始から181日目以降は50%)
ここではシンプルにポイントだけお伝えしたいので「休業開始時賃金日額」ってなに?などの説明は省略いたしますが、シンプルに上記の赤線部分がポイントです。180日≒約半年を過ぎると、給付金額が下がります。
正直、たかぼん家は準備不足で、手当がどの程度なのかをあまり気にしていなかったがために、支給額がどの程度なのかを計算しておらずシンプルに半年過ぎると給付金下がるの微妙、、、?くらいの感覚で「復職のタイミングともちょうどいいし半年くらいにしようか」くらいの感覚でした。
逆に、半年過ぎても50%も貰えるのか!ラッキー!というご家庭もあるかもしれません。
事前に、生活費とご夫婦の支給額を照らし合わせ、生活水準を維持できるのか、はたまた工夫が必要なのかなど、ある程度想定された方がベターかと思います。
社会保険料の免除について
社会保険料の免除は月区切り!
私は社会保険料の免除について大きく気にしなかったのですが、押さえておくべきポイントは、月初を育休開始にしない、ということです。社会保険料に日割計算はありませんので、1日ずれるだけで、1ヶ月分の社会保険料が変わります。
例えば、10月1日を育休開始にするのではなく、9月30日を育休開始にした方が絶対お得です。
10月1日を開始にした場合は9月給与分の社会保険料は免除になりませんが、9月30日を開始にしておけば、9月分の社会保険料が免除になるからです。
尚、育休期間中の社会保険料免除要件は、以下になります。
給与に係る社会保険料の免除要件
- 育児休業等の開始日が属する月から、終了日の翌日が属する月の前月まで
- 児休業等を開始した日の属する月内に、14日以上(休業期間中に就業予定日 がある場合は、当該就業日を除く。また、土日等の休日も期間に含む。)の育児休業等を取得した場合
賞与に係る社会保険料の免除要件
- 賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合
私の周りでは1ヶ月以上の取得が一般的なので、それをベースにお話しすると、開始月は保険料免除、終了月の最終日(翌月の前日)を終了日にしておけば、終了月も保険料が免除になる、程度に認識しておけばOKだと思います。
育休中の保険料免除については様々なサイトで図やグラフにしてわかりやすく示してくれていて、私には到底にそれに勝る図が描けそうになかったので、詳細を確認したい場合は私が参考にしたサイトをご覧いただければと思います。
有休消化について
なるべく有給が余らないように工夫を!
私は、会社には申し訳ないと思いながらも、次の有給付与のタイミングに合わせ、なるべく有給が消滅しないように調整しました。(それでも消滅しましたが、、。)
育休に入る直前で付与された場合は、育休開始日を月末にずらし、ずらした分を有給で調整するのもアリだと思います。ただ、育休復帰後にも有給を使う可能性はもちろんあるので、復帰後の有給残のことも考えながら調整するのが良いかと思います。
賞与査定期間と育休期間について
賞与査定期間になるべく被らないように調整を!
これは会社により期間やルールが異なるかと思いますが、私の会社の場合、5〜10月が冬のボーナスの査定期間、11〜4月が夏のボーナスの査定期間です。
会社のルール上、育休中は査定期間に含まれない場合があるため、なるべく査定期間が長くなるように調整しました。(前述した有給などで)
さて、一旦以上です。
冒頭申し上げた通り、考え方やご家庭の状況や出産予定日、保育園or幼稚園など、状況により悩む箇所が大きく変わってくる育休期間ですが、検討すべきポイントはおおむね一緒なのではないでしょうか。
悩まれているご夫婦に少しでも参考になればと思います。
ではまた!
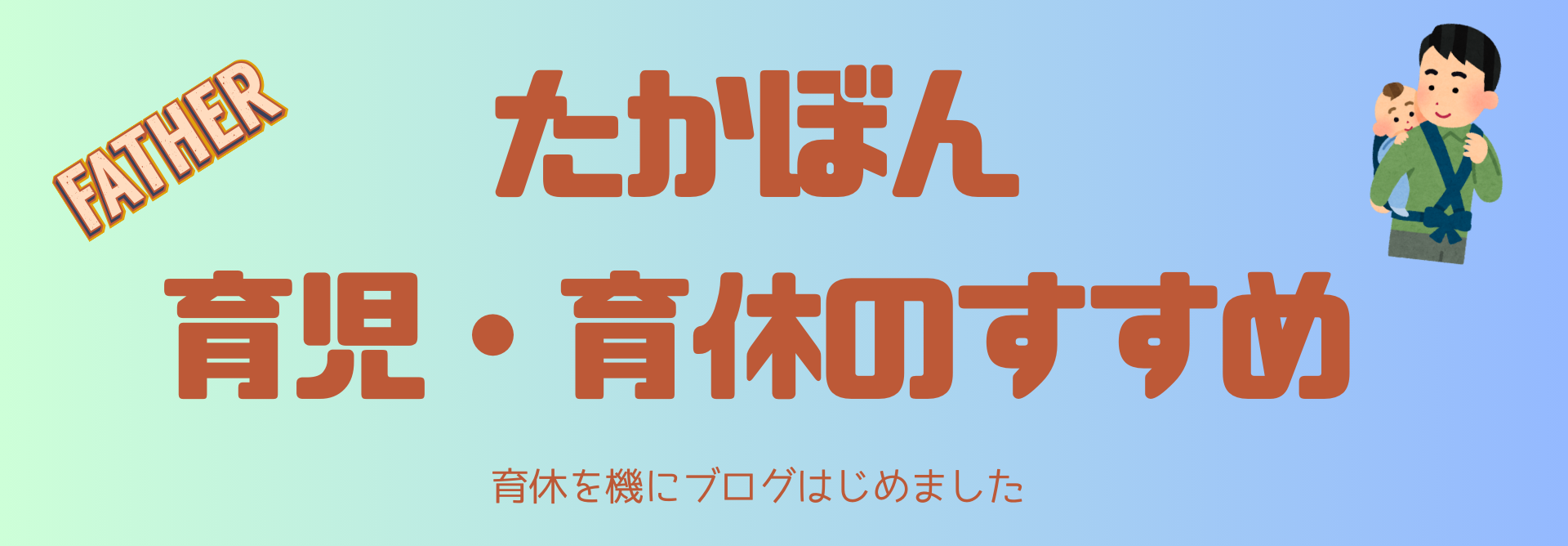



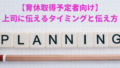
コメント